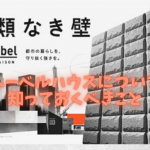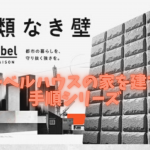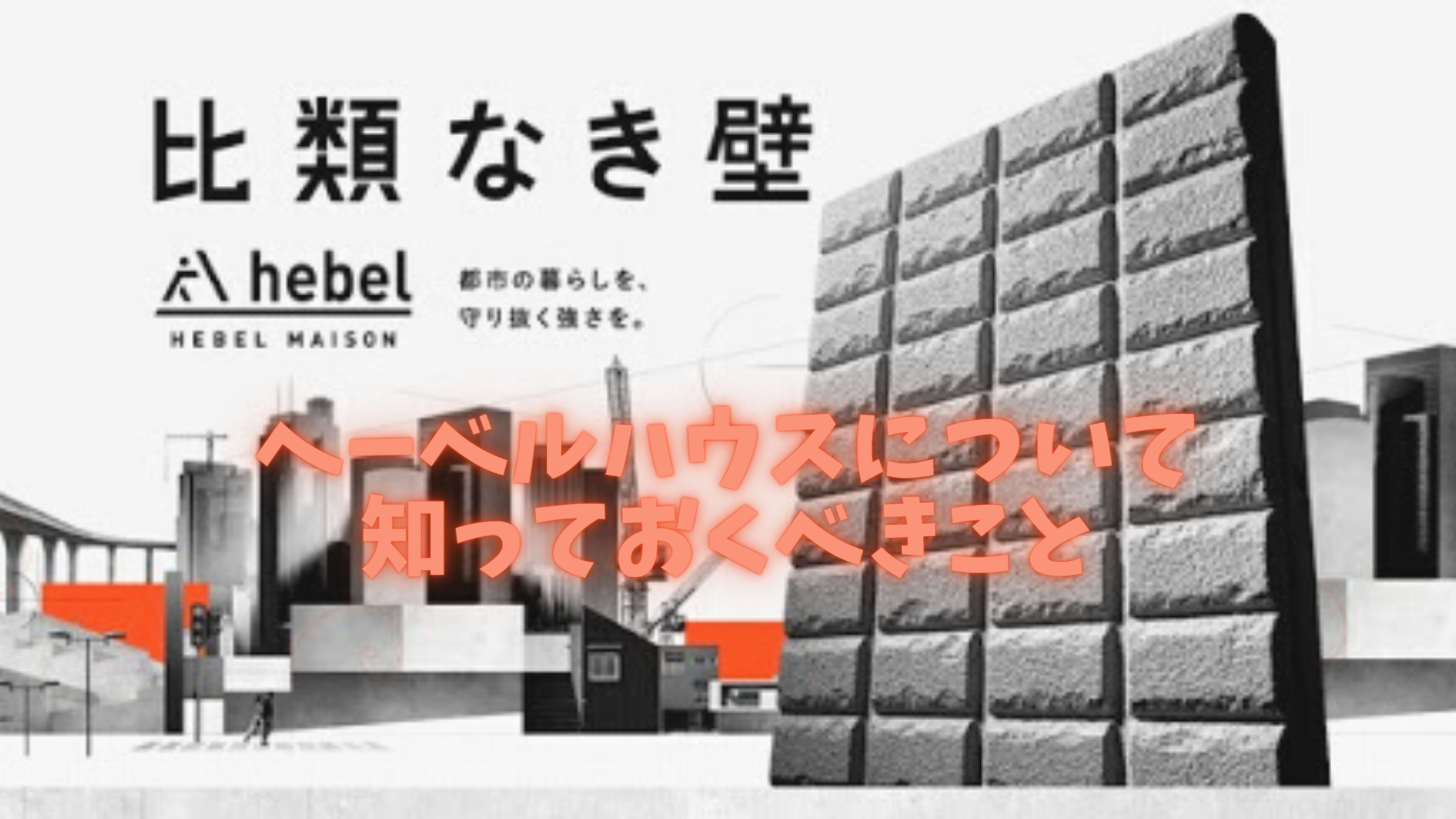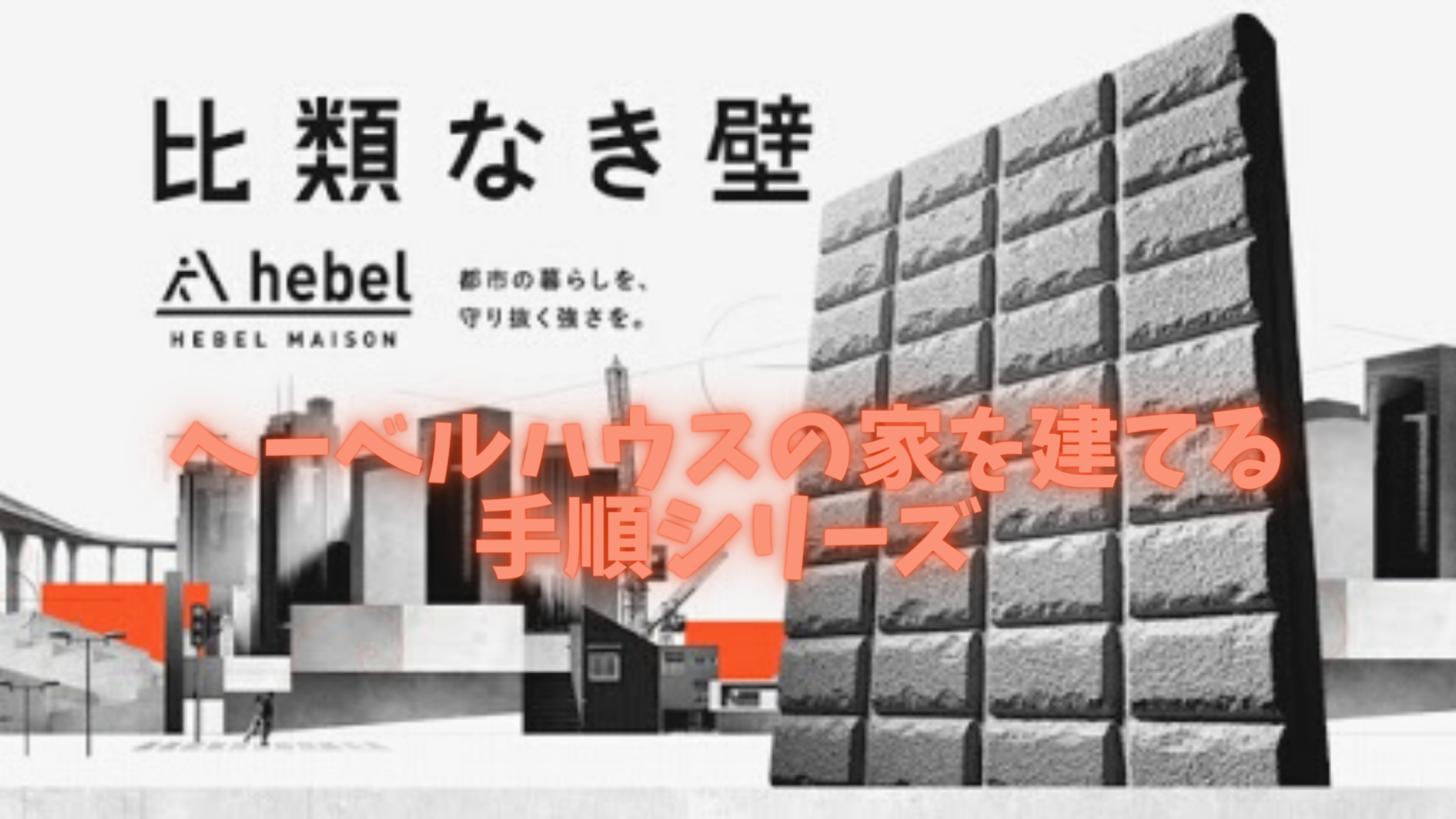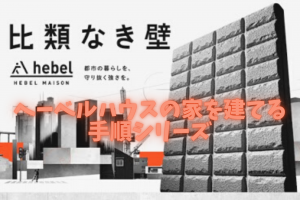間が空きましたが、ヘーベルハウスの家を建てる手順シリーズもいよいよ着工という段ではありますが…
先日Twitterで何件か拝見した件で、多くの家造り中の施主さんがハマっている問題を見つけましたので、着工編に入る前にこの部分を軽くおさらいしようと思います。
変更に伴う追加費用が発生するタイミングについて、業者側と揉めるケースについてです。
注文住宅を建てるなら、少しでも理想に近づけたい!とは誰もが思うでしょう。
打ち合わせの中で、やっぱりここはこうしたい!という思いが出てきて、途中で間取りやら設備やらを変更したくなるケースは多いと思います。
その変更について、タイミングによっては変更に伴う商品の差額以外に、変更に関わる手数料が追加でかかるケースも出てきます。
業者側の担当者によってはきちんとそのタイミングについて説明してくれる人もいれば、ちゃんと説明してくれない人もいます。
そこで今回は、どの時点での変更なら追加費用が掛からないのか?という点を扱おうと思います。
Contents
決定と変更のタイミング
ハウスメーカーと呼ばれる様な企業の場合、家造りはシステマティックにスケジュールが立てられて打ち合わせが進みます。会社によって若干の順番や進め方の差はありますが、他の会社で建てた施主の話を聞く限りだと大体似たようなものなので、ヘーベルハウスでの実例を元に決定と変更リミットについて扱います。
家造りのスケジュール
これはヘーベルハウス公式にあるスケジュール表です。
上記の図の①から⑤の行程で、最初の見積額が決定します。
そして、⑦の行程で大体の施主の皆さんは金額が上振れします。これはもう、そういう宿命なのですが、それは追々。
そして、⑧の変更契約(一部のハウスメーカーでは着工合意なんて言いますね)で、金額が完全にFixして、いよいよ着工という流れになります。
では、次のセクションから費用が決まっていく要所要所の説明をしていきます。
行程と確定リミット
上記のヘーベルハウス公式の行程表ではちょっと説明しづらいので、必要な個所をピックアップして行程表を私なりに作ってみました。要所要所をセクションを区切り説明します。

間取りは建築確認申請までが事実上のリミット
家を建てるには、建築確認申請というお役所への届け出が必要です。ハウスメーカー側によく確認した方が良いのは、いつの時点の間取りで建築確認申請を出すのか?という点です。
と言いますのも、ハウスメーカーで建築する場合は最初の契約時点の間取りで建築確認申請を通すケースが多いです。
この建築確認申請ですが、勿論後から変更もできるのですが、変更の内容次第で「計画変更」という追加費用が掛かる変更が必要になるケースがあります。
具体的にどんな変更が発生すると、「計画変更」の対象となるのかは大体以下の通りです(明らかに施主サイドで変更しないだろうという項目は省いています)。
| 建物の位置の変更 |
| 敷地面積の減少 |
| 建築物の高さの増加 |
| 階数の増加 |
| 建築面積の増加 |
| 平面間仕切りの変更 |
| 壁の長さが変わる 又は 開口部ができる |
| 排煙口の位置の変更 |
| 排煙有効面積の増加 |
| 排煙有効面積の減少 |
| 排煙機能力の変更 |
| ダクト・排煙ダクトの変更 |
| 換気設備の変更 |
| 非常用照明の減少 |
| 構造の変更 |
| 基礎の変更 |
| スパン(支点間距離)の増加 |
| スパン(支点間距離)の減少 |
| 2次部材の変更(耐力が減少する場合) |
| 構造計算の変更 |
| 建築物の軒高増加 |
| 地盤面の変更 |
| 杭の変更 |
| 屋根、軒、軒裏、ひさしの変更 |
そこで上記の図に戻ってほしいのですが、フェーズ①の時点で既に間取りを決めて契約締結に至っていると思いますが、ヘーベルハウスではその後の住設決定(風呂・トイレ・キッチン)を行った後すぐに建築確認申請に回すというスケジュールになっているので、この段階以降での間取りの変更など、上記で挙げた「計画変更」に該当するような変更は追加料金の対象になりうるという点を意識して打ち合わせに臨んでください。
計画変更を伴う変更フェーズは、上記の図で言う「エクストラフェーズ」の部分に該当します。ヘーベルハウスの場合、このエクストラフェーズに入ると、追加の手数料分が見積もりに加算されるケースが多いです。
また、確認申請自体にも時間がかかるので、着工前の確定契約でもある「変更契約」時期ギリギリに大幅な間取り変更をしてしまうと、着工時期も計画より後ろ倒しになります。
そもそも家の大きさや間取り変更は建築費用の大幅な増加にもつながるので、間取りが決まるまで契約を締結しないくらいのつもりで打ち合わせに臨むのが良いかもしれません。
一部、サイズダウンするだけであれば「計画変更」ではなく、「軽微な変更」の扱いとなるケースもあります。
変更申請費用も「計画変更」よりも安いので、結果的に見積額の減額効果もあってトータルで当初の見積もりよりマイナス見積となることもあるので、間取りFix後は絶対に変えない!と固執せずに、打ち合わせを進めるにあたって建築確認申請とそれに係る諸々手数料はどうなるのかも担当営業にしっかりと聞いて計画を進めることが大事です。
追加費用云々を抜きに、間取り変更のリミットはいつなのか?については、上記の図の「変更契約」がリミットです。
原則、この変更契約後にはもう間取り変更はできないと認識してください。どうしても悩むのであれば、「変更契約」の時期を後ろ倒しにして、当初契約時の引き渡し期限日も合わせて後ろ倒しにすることが必要になります。
※ハウスメーカーでは当初契約時に引き渡し時期を決めて契約を実施するため、途中の打ち合わせが遅滞すると変更契約の時期も後ろにずれるため、必然的に着工時期もずれます。ずれた分引き渡し時期も遅くなるという認識を持ちましょう
※室内建具を開き戸から引き戸に変更等も、この建築確認申請のリミットに係るケースがあるので注意してください
部材発注のタイミングが事実上のリミット
家の間取りは事実上フェーズ①がリミットと考えないと、追加費用が発生する要因となるというお話を前のセクションで扱いましたが、インテリアなどの内装部分のリミットについてここでは扱います。上記フェーズ②に該当するのですが、間取りを決定し、住設(風呂・トイレ・キッチン)を決めた後(フェーズ①行程)は、いよいよインテリアの検討に入っていきます。
ここでまず大事なのは、住設です。
例えばお風呂ですが、ヘーベルハウスでは標準ラインナップの中からTOTO、Lixil、セキスイからユニットバスを選択できるのですが、サイズを変更さえしなければ建築確認申請に影響しないので変更が可能です。
可能なのですが…問題は発注のタイミングです。
実際に我が家は当初、キッチンをトクラスをチョイスしていたのですが、途中でやはりLixilの方が良いということでLixilのキッチンに変更しました。
この変更、実際に発注を出すタイミングより前だったので何とかなったのですが、既に部材発注済みだと変更不可もしくは、変更するにも追加の手数料がかかります。
インテリアを決めていくうちに、やはりキッチンなどを変更したくなるのは人のサガ(?)です。
しかし、いざインテリアを決めていく中で、フェーズ①行程で決定済みの住設を変更したい!と思った時に手遅れだとテンションが大幅に下がってしまいます。
皆様にお勧めしたいのは、「住設の変更はいつまで可能でしょうか?」とインテリア打ち合わせのスタート前には聞いておくことです。
ヘーベルハウスでは専属のインテリアアドバイザーがついてくれるのですが、イメージに合わせるために住設を変更したいという相談にも乗ってくれます。
変更のための調整も行ってくれるので、いつまでに変更を決定すれば間に合わせてくれるか?をしっかり話し合い、それに合わせてインテリア打ち合わせの中で住設の最終決定を進めることも可能です。
インテリア打ち合わせを進めていくと、床材、壁紙、建具、照明等を決めていくことになります。
これらにも発注期限があります。これらも、住設同様発注した後に変更となると、変更手数料がかかります。
廃番品の発注
壁紙など一部の製品は、廃番となって在庫限りとなっているケースもあります。発注タイミング的にはもう少し後工程でも、在庫限り品を押さえるために先に発注をかけてくれるケースもあります。
そこで、発注していたものをやっぱりやめたとなると、やはり変更手数料が追加でかかるケースもあるので、担当者によく確認するようにしてください。
モデルチェンジの扱い
この記事を執筆している2022年1月末時点で、Lixilのユニットバスのアライズがモデルチェンジをするという情報が入ってきています。丁度このタイミングで家造りの打ち合わせをしている方もいらっしゃるかもしれませんが、既に打ち合わせの中で従来製品で仕様を固めているケースでは、担当者がわざわざモデルチェンジがあった旨を知らせてくれるかどうかはわかりません。
その辺の情報アップデートに敏感な担当者は、新型が出ましたがどうしますか?と問いかけてくれるかもしれませんが、敏感じゃない担当者の場合は特に触れないかもしれません。
なるべく新型を入れたいと思っているのなら、自分でも情報を収集するよう心掛けてください。そして、担当者に「新型が出たようだけど、我が家への導入に間に合うのか?」を聞いてみてください。
もしかしたら、発注リミット前なら何とかなるかもしれません。
まとめ
注文住宅での打ち合わせを進めていく中で、色々決め事があり、その決め事の変更はいつまで可能なのか?いつまでなら追加費用が掛からないのか?という点を今回は扱いました。長々と書いてきましたので、簡単にまとめます。
まず、大前提として着工契約ともなる「変更契約」の締結以降の変更は不可能と考えてください。
※追加費用を惜しまないのであれば、変更が可能な部分はあります
間取り変更リミット
- 間取りは建築確認申請を出す前ならいくらでも変更は可能
- 建築確認申請を出した後の間取り変更は追加費用の対象と考えておく
- 費用と引き渡し日の延期を度外視するのであれば、「変更契約」を締結するまでであれば間取り変更は可能
- 「変更契約」後の間取り変更は原則NG
- 着工後はもっとNG
住設やインテリアの変更リミット
- 「変更契約」締結までは原則変更は可能
- ただし、部材発注が済んでいるものは変更手数料がかかるケースがある
- 住設などモデルチェンジがあっても自動的に最新モデルに変更はしてくれないので自分で頼む必要がある
以上、変更手数料がかかることなく変更が可能な期限のポイントとしては、「建築確認申請」を出すまでと、「部材発注」を出すまでというポイントを意識して、担当者と期限感をしっかりと認識合わせをしましょう。
『無理を通せば道理が引っ込む』という言葉もありますが、なんだってイレギュラーなことをあまりやると、ミスは増えるものです。
貴方の生活の基盤となる家なので、ミスは極力起こしてほしくないものだとは思いますが、施主がミスの原因となるような無茶振りをしないことも大事な要素です。
今回扱った、変更リミットの部分もしっかり意識するのも、良い家造りの大事な要素だということを忘れないでくださいね。
今回は以上です。