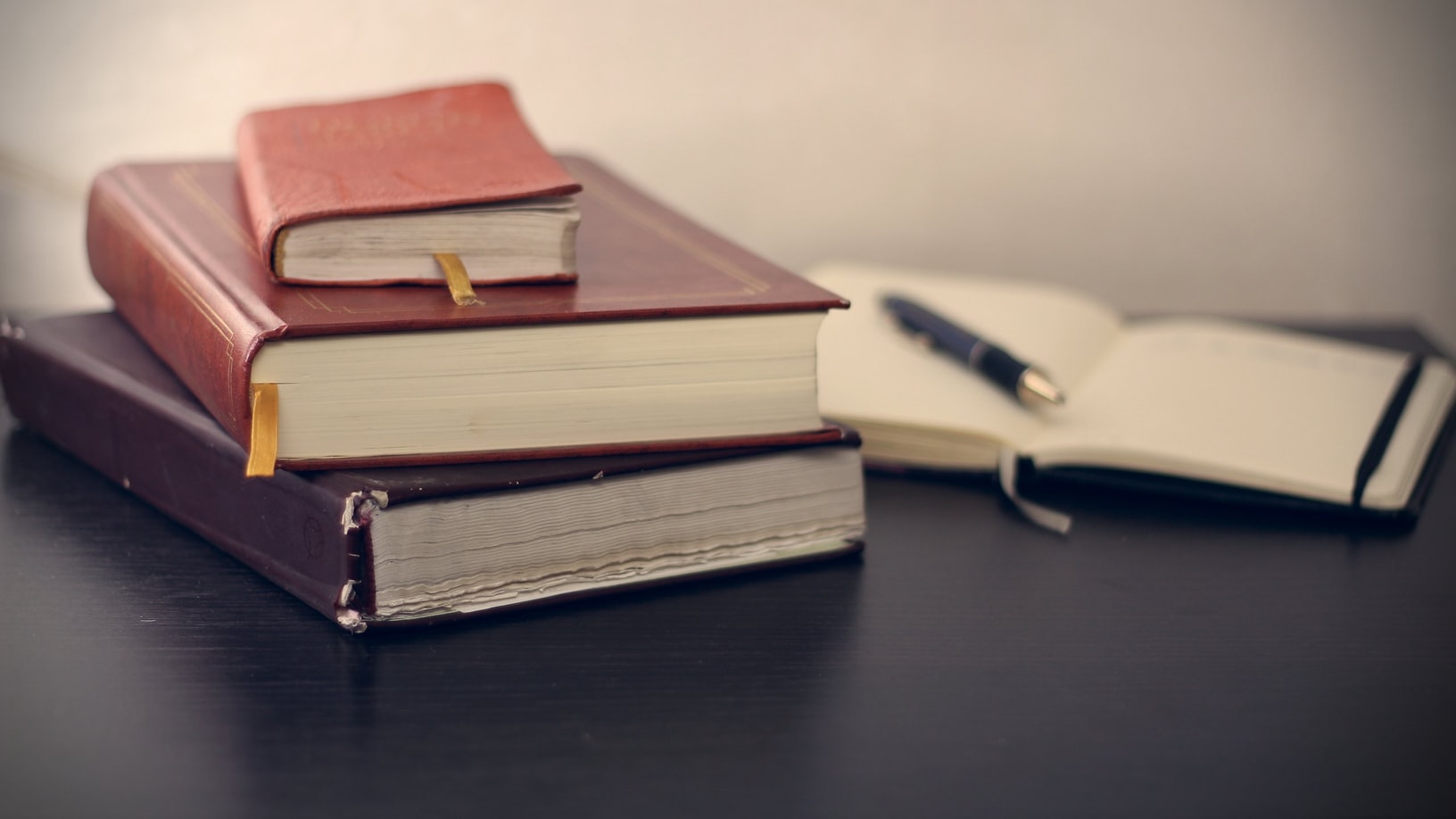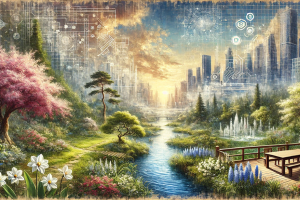前回まで、今回の改正のポイントのうち、①ログイン型投稿に関する開示対象と開示要件を取り扱ってきましたが、今回からは、改正のポイントの2点目、②発信者情報開示に関する新たな裁判手続について説明します。初回の今回は、新しい手続の簡単な紹介と、従前の制度との関係についての説明を行います。 新たな裁判手続は、基本となる(1)発信者情報開示命令(8条)と、これに付随する(2)提供命令(15条)、(3)消去禁止命令(16条)の3つの命令手続からなります。 このうち、(2)提供命令は、従来の制度と大きく異なる手続であり、新制度の特徴ともいえます。 (発信者情報開示命令) (提供命令) 一 当該申立人に対し、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該イ又はロに定める事項(省略)を書面又は電磁的方法(省略)により提供すること。 イ (省略) ロ (省略) 二 この項の規定による命令(以下この条において「提供命令」といい、前号に係る部分に限る。)により他の開示関係役務提供者の氏名等情報の提供を受けた当該申立人から、当該他の開示関係役務提供者を相手方として当該侵害情報についての発信者情報開示命令の申立てをした旨の書面又は電磁的方法による通知を受けたときは、当該他の開示関係役務提供者に対し、当該開示関係役務提供者が保有する発信者情報を書面又は電磁的方法により提供すること。 2 (以下省略) (消去禁止命令) 2 (以下省略) 今回の改正による新しい手続は、当初、従前の訴訟手続に代わるものとしての導入が提案されましたが、結局、従前の制度に加えて創設されることとなり、新旧の制度が併存することとされました。 したがって、改正後も、従前どおり訴訟手続を用いることも可能であり、また、裁判外で請求を行うことも可能とされており、どの手続を用いて請求を行うかは、権利者の選択に委ねられることとなります。 新旧制度が併存することとされたため、権利者は訴訟手続によるか、新制度の発信者情報開示命令を求めるか、手続の選択が可能です。 もっとも、新手続で発せられる決定は、条件を満たすと確定判決と同様の効力を有することとされていることから(14条5項)、民事訴訟法の重複起訴の禁止の規定(142条)の適用を受けると考えられます。 そのため、訴訟手続と新手続(発信者情報開示命令)を同時に申し立てることはできず、権利者は、どちらか一方を選択して申し立てる必要があります。 〇民事訴訟法 新たな裁判手続として、基本となる発信者情報開示命令とそれに付随する提供命令、消去禁止命令の各手続が設けられた。 新たな裁判手続の創設によっても、従来の訴訟手続を用いることは可能であり、手続の選択は権利者に委ねられている。ただし、両方の手続を同時に申し立てることはできない。 次回も引き続き、改正のポイントの2点目の発信者情報開示に関する新たな裁判手続を取り扱い、手続の具体的内容に入っていく予定です。
1 新たな裁判手続
第8条 裁判所は、特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者の申立てにより、決定で、当該権利の侵害に係る開示関係役務提供者に対し、第5条第1項又は第2項の規定による請求に基づく発信者情報の開示を命ずることができる。
第15条
1 本案の発信者情報開示命令事件が係属する裁判所は、発信者情報開示命令の申立てに係る侵害情報の発信者を特定することができなくなることを防止するため必要があると認めるときは、当該発信者情報開示命令の申立てをした者(省略)の申立てにより、決定で、当該発信者情報開示命令の申立ての相手方である開示関係役務提供者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
第16条
1 本案の発信者情報開示命令事件が係属する裁判所は、発信者情報開示命令の申立てに係る侵害情報の発信者を特定することができなくなることを防止するため必要があると認めるときは、当該発信者情報開示命令の申立てをした者の申立てにより、決定で、当該発信者情報開示命令の申立ての相手方である開示関係役務提供者に対し、当該発信者情報開示命令事件(当該発信者情報開示命令事件についての第14条第1項に規定する決定に対して同項に規定する訴えが提起されたときは、その訴訟)が終了するまでの間、当該開示関係役務提供者が保有する発信者情報(省略)を消去してはならない旨を命ずることができる。
2 従前の制度との関係
3 訴訟手続と新手続(発信者情報開示命令)の同時申立ての可否
(重複する訴えの提起の禁止)
第142条
裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。
ポイント