第48回 住宅(不動産)にかかわる民法改正の概要(3)
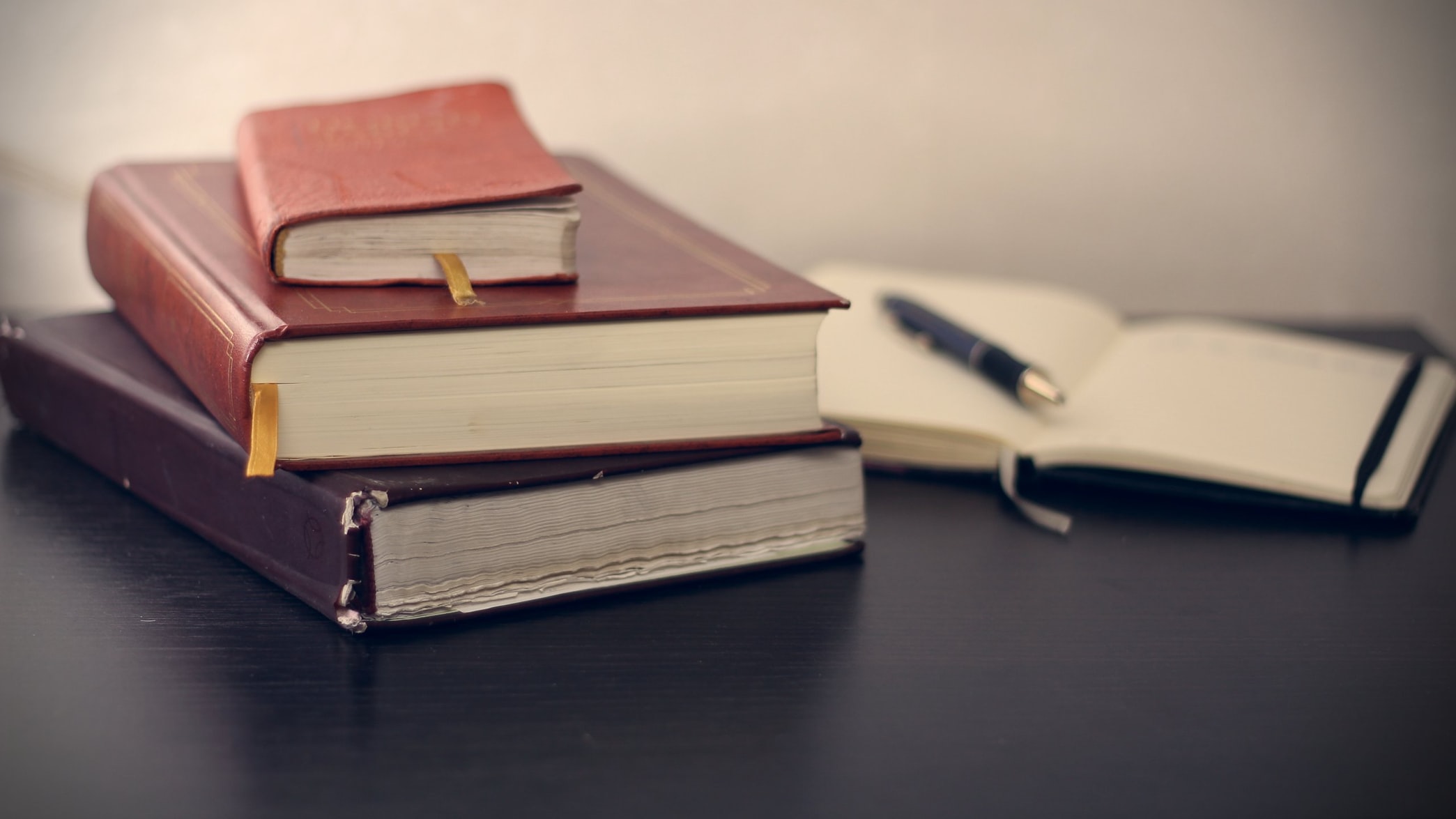
今回は住宅(不動産)にかかわる民法改正の第3回です。今回から、売買契約に関わる改正の中心の一つとされている担保責任(契約不適合)の問題をみていきます。
1改正前の規定
当事者が給付した目的物や権利に瑕疵がある場合に当事者が負う責任のことを担保責任といいます。売買契約における売主の担保責任に関し、改正前は、①権利の全部または一部が他人に属する場合、②目的物に用益物権や抵当権などの他人の権利が設定されている場合、③目的物に隠れた瑕疵がある場合などについて、それぞれ一定の要件のもと、買主に損賠賠償請求や契約解除などを認める定めが個別に置かれていました(改正前561条以下)。
しかし、これらの担保責任については、その法的性質をめぐる解釈の対立(法定責任説と契約責任説)があるなど、一般の債務不履行責任との関係が明らかになっておらず、学説上も議論が重ねられてきました。なお、判例(最判昭36・12・15民集15-11-2852)は、典型的な法定責任説の立場をとらないことは示しましたが、特定の説を採用することまでは述べていません。
2改正法の概要
上で述べた改正前の担保責任をめぐる問題を踏まえ、今回の改正では、契約の内容に適合した目的物の引き渡し・権利の移転を行うべき義務を承認することを前提として、その義務が履行されなかった場合の買主の救済手段について統一的な規定が定められ、抜本的な変更が行われました。この変更は、これまでの学説の対立について、契約責任説を採用することを明らかにしたものと言われています。
これにより、改正前は、売買の目的が物の場合と権利の場合とを分けて個別に規定され、一般の債務不履行責任とは異なるものとして理解されることもあった売主の担保責任について、物・権利に関する契約不適合を理由とする債務不履行責任の規定として整理、統合されることになりました。
このように契約責任説に基づく改正が行われた理由としては、①特定物に瑕疵があっても債務不履行を構成せず、売主の追完義務は否定される(現状で引き渡せば足りる)という法定責任説の考え方は、工業製品等の種類物が売買の目的の中心となっている現代の実務に適合しない、②権利に関する売主の責任についても、売主が権利の移転をどこまで引き受けていたかの契約解釈が重要であり、当事者の引き受けた契約内容に適合した権利を移転する義務に対する不履行として定めるべき、といった点が挙げられています。
3売買契約以外の契約における担保責任
今回の改正で採用された、契約の内容に適合した物の引き渡し・権利の移転を行う義務を承認したうえで、その義務に対する債務不履行責任として担保責任をとらえ直すという考え方は、売買契約だけでなく、贈与契約、使用貸借契約、請負契約といった、他の契約類型においても、同じように当てはまると考えられています。
そのため、売買契約以外の契約類型においても、契約の内容に適合した物・権利を供与すべき義務に対する債務不履行責任と位置付けた場合に、各契約の特質によって、特に一般の債務不履行の規定と異なる内容の規定が必要とされる場合に限って、個別の規定が置かれることとされました。
こうした改正により、改正前の570条などに用いられていた物や権利の「瑕疵」という表現は、以下の参考条文のように「契約の内容に適合しない」という表現(「契約不適合」と呼ばれます)に改められ、この表現は、他の契約類型における担保責任の規定(請負契約に関する636条等)においても同様に用いられています。
562条1項
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
契約内容に適合した目的物・権利を供与すべき義務を売主が負うことを承認したうえで、そのことを前提に各種の担保責任に関する規定が改正された。
物や権利の瑕疵について、個別の場面に応じて細かく定められていた担保責任の規定を改め、契約不適合を理由とする債務不履行責任として整理・統合して規定された。
次回も、引き続き担保責任(契約不適合)の問題を取り扱い、改正法における救済手段をみていく予定です。
 このコラムの執筆者
このコラムの執筆者原田真(ハラダマコト)
一橋大学経済学部卒。株式会社村田製作所企画部等で実務経験を積み、一橋大学法科大学院、東京丸の内法律事務所を経て、2015年にアクセス総合法律事務所を開所。
第二東京弁護士会所属。東京三弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会副委員長、同高齢者・障害者の権利に関する委員会副委員長ほか
コラムバックナンバー
-
第48回 住宅(不動産)にかかわる民法改正の概要(3) New!

-
第47回 住宅(不動産)にかかわる民法改正の概要(2)

-
第46回 住宅(不動産)にかかわる民法改正の概要(1)

-
第45回 プライバシー侵害の救済方法(7)

-
第44回 プライバシー侵害の救済方法(6)

-
第43回 プライバシー侵害の救済方法(5)

-
第42回 プライバシー侵害の救済方法(4)

-
第41回 プライバシー侵害の救済方法(3)

-
第40回 プライバシー侵害の救済方法(2)

-
第39回 プライバシー侵害の救済方法(1)

-
第38回 プライバシー侵害の成立要件(5)

-
第37回 プライバシー侵害の成立要件(4)

-
第36回 プライバシー侵害の成立要件(3)

-
第35回 プライバシー侵害の成立要件(2)

-
第34回 プライバシー侵害の成立要件(1)

-
第33回 名誉毀損の救済方法(12)

-
第32回 名誉毀損の救済方法(11)

-
第31回 名誉毀損の救済方法(10)

-
第30 名誉毀損の救済方法(9)

-
第29回 名誉毀損の救済方法(8)

-
第28回 名誉毀損の救済方法(7)

-
第27回 名誉毀損の救済方法(6)

-
第26回 名誉毀損の救済方法(5)

-
第25回 名誉毀損の救済方法(4)

-
第24回 名誉毀損の救済方法(3)

-
第23回 名誉毀損の救済方法(2)

-
第22回 名誉毀損の救済方法(1)

-
第21回 名誉毀損の成立阻却事由(6)

-
第20回 名誉毀損の成立阻却事由(5)

-
第19回 名誉毀損の成立阻却事由(4)

-
第18回 名誉毀損の成立阻却事由(3)

-
第17回 名誉毀損の成立阻却事由(2)

-
第16回 名誉毀損の成立阻却事由(1)

-
第15回 名誉毀損の成立要件(4)

-
第14回 名誉毀損の成立要件(3)

-
第13回 名誉毀損の成立要件(2)

-
第12回 名誉毀損の成立要件(1)

-
第11回 近隣紛争(2)

-
第10回 近隣紛争

-
第9回 住宅の相続に関する問題

-
第8回 土地の境界に関する問題

-
第7回 建物建築工事契約の留意点

-
第6回 建物の建築が制限されるケース

-
第5回 不動産登記の基礎の基礎

-
第4回 法的観点からみる住宅ローン

-
第3回 売買契約締結後のトラブル(2)

-
第2回 売買契約締結後のトラブル(1)

-
第1回 住宅、土地の購入と契約の解消


















