第7回 工事着工から完成までの注意点

契約した後、現場で工事に着手すれば、期待も不安もあることでしょう。多くの人が建築中の現場へ足を運びますが、やってはいけないことがあるので理解しておきましょう。現場での施主の態度・対応が原因で建築トラブルになることも多いです。
1現場での基本的な心得え
建築中の様子が気になり現場へ見学に行くことは構いませんが、基本的な心得を抑えておかないと無用なトラブルを誘発することになりかねません。
1-1.土地所有者でも原則、現場では建築会社に従う
建設現場に見学へ行くとき、仮にその土地が施主の所有するものであっても、現場の管理は建築会社の責任で行われていることをよく理解しておくべきです。自分の土地だから自由に出入りしてよいというわけではありません。
建築会社にしてみれば、安全管理という重要な責務があります。自由に、ヘルメットも付けずに出入りされたのでは、建築会社としてもたまったものではありません。また、関係悪化につながることもあるでしょう。
1-2.現場で職人等の邪魔をしない
現場見学の際、気になる箇所などがあれば、作業中の大工、各種職人などに質問攻めをしている人がいます。気になることがあるわけですから、気持ちはよくわかりますが、やりすぎた場合には現場の効率を悪化させることにもなりかねません。
工事が遅延したとき、こういったことを理由として挙げられ、ひどい場合にはかえって遅延の責任を求められることもありうるので、注意しましょう。
また、職人等が現場で休憩している時間帯に訪れて、同じように質問攻めするのもよくありません。きちんと休憩をとって心身ともにきちんと管理してもらいつつ、工事を進めてもらうことを優先すべきです。
1-3.担当者の同行が理想
少し理想論になりますが、現場見学の際には、施主の窓口となる担当者に同行して頂きたいものです。担当者とは会社などにもよりますが、営業担当であったり、設計や現場の担当であったりするでしょう。しかし、一度や二度ではなく何度も担当者に同行してもらうのは現実的ではありません。担当者も多くのお客様を抱えており忙しいことでしょう。
よって、現場見学へ行く際は担当者に連絡しておくこと、そして現場で気になることはあまり職人等に言わず、担当者に電話やメールなどで質問することを基本とした方がよいでしょう。また、会社によって現場に関する質問等については誰が対応するのか決めていることもありますから、そういったルールの確認もしておきましょう。
2追加・変更工事の注意点
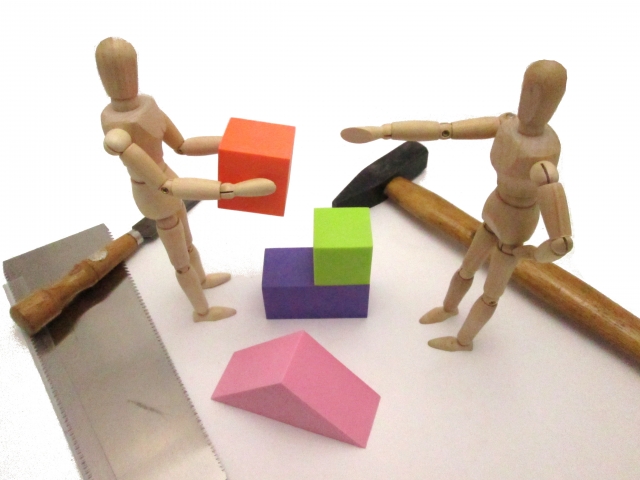
建築途中で施主側からプランの一部について変更や追加工事を依頼することもあります。これに対応するかどうかは、工事内容や時期を考慮したうえで建築会社が判断することになります。そういった追加や変更工事に関する注意点を紹介します。
2-1.現場で大工等に追加・変更工事を直接依頼しない
追加や変更工事はトラブルの基となることが非常に多いです。トラブル発生のよくあるパターンが、施主による現場への直接指示、直接依頼です。
現場見学時に気づいたことを、その場で勝手にどんどん指示、依頼してしまう人がいますが、それによって他の工事に悪影響を及ぼしたり、金銭トラブルに発展したりしています。
2-2.追加・変更工事は見積りを確認する
追加や変更工事については、職人等に指示・依頼せず、担当者を通して行いましょう。その際、正式に発注する前に変更や追加によって生じる費用について見積りを書面で確認しましょう。この作業を怠ることで、後々に想定外の費用を請求されて建築会社ともめる人は多いです。
これぐらいは簡単にできることだろうからと安易に考えず、見積りを確認してから進めることを基本としてください。
3工期・工事進捗を確認する
建築工事が予定よりも遅れることは少なくありません。当初の工程表の通りに進まず、完成が1カ月単位で遅れることもあります。遠方であること等を理由にあまり現場見学に行かない人もいますが、工事の進捗に遅れが出ていないか確認しておく方が良いです。
工事が遅延しているならば、当然に建築会社の方から報告があがるはずだと考えるかもしれませんが、その当然の行動ができない担当者が残念なことに少なくありません。
忙しくて時間がない場合であっても、工事の節目(基礎工事の完了時・上棟時・防水工事など)では時間を作って施主自身の目で確認した方がよいでしょう。
4施工品質をチェックする
施主が建築途中にしておきたい重要なことの1つが施工品質のチェックです。簡単にいえば、欠陥工事・施工ミスが起こっていないか確認することです。施工ミス等の影響によって、入居後に悩まされる人も少なくありません。
完成済みの建売住宅を購入するのとは異なり、せっかく建築中にチェックすることができるのですから、その良い機会を活かしたいものです。
4-1.基礎配筋・上棟後には現場で報告を受ける
施工品質の1つの確認方法としては、建築会社から現場で説明・報告を受ける方法があります。ハウスメーカーによって、積極的に現場説明会を開催することもありますが、要望しないと実施してくれないことも多いです。また、要望しても満足に対応してもらえないこともあります。
その建築会社が可能な範囲で、現場説明会を実施してもらうようお願いしてみましょう。基礎工事や上棟後の2回は最低限度、確認しておきたいタイミングです。
4-2.第三者検査の活用
建築会社の現場説明会は、万能なものではありません。何度も何度も実施できるわけではありませんし、そもそもその会社の説明内容が真実であるという前提で説明を受けることになるからです。ミスをきちんと説明してもらえるのであればよいのですが、現実はそう希望通りにいくものではありません。
また、建築は専門的なことばかりですから、少々勉強したとしても自分で細かくチェックするのは無理があります。そこで、第三者の立場で行う住宅検査会社へ依頼する人も増えています。建築会社から、第三者機関が検査していると説明を受けることもありますが、その第三者機関とは別ものです。
建築会社がいう第三者機関は、瑕疵担保責任保険の加入等のために実施する検査ですが、これらはその基準に適合するかどうかを確認するのみで、様々な工程で幅広く検査を実行するわけではありません。この種の検査はどの住宅でも利用されていますが、建築トラブルはいつまでもなくなっていません。
ここでいう第三者の住宅検査会社とは、施主が自分で検査会社を探して依頼する先のことで、先に挙げた第三者機関より細かな範囲まで施工不良の有無をチェックしてくれます。
5中間金の支払い

注文建築の取引では、契約内容によって中間金の支払いが必要なこともあります。工事請負代金は、契約時に支払う手付金、工事中の出来高に沿って支払う中間金、そして完成時に支払う残代金に分けて支払うのです。
ただ、中間金は契約によっては無いことも多いです。その場合、手付金と残代金のみの2回の支払いということです。中間金がある取引の場合、中間金そのものが1~3回程度に分けられていることもあります。
中間金は出来高に応じて支払う金銭ですから、どの工程まで進んだときにいくら支払うものか、契約書で明記しておくべきです。そして、その通りのタイミングで支払わなければなりません。建築会社から中間金の支払い時期を告げられたときは、そのタイミングで現場見学を行い、工事が予定の工程まで進んでいることを確認してから支払うようにしてください。
この現場見学の際に、前述した建築会社による現場説明会を実施してもらうようにしておけば、効率的であり、工事の進捗確認もしやすいので、お勧めです。
 このコラムの執筆者
このコラムの執筆者荒井 康矩(アライ ヤスノリ)
2003年より住宅検査・診断(ホームインスペクション)、内覧会同行、住宅購入相談サービスを大阪で開始し、その後に全国展開。(株)アネストブレーントラストの代表者。
コラムバックナンバー
- 第25回 耐震性を考えるなら新耐震基準の中古住宅購入(最終回)

- 第24回 中古住宅を買うなら住宅ローン控除の手続きを忘れないように

- 第23回 中古住宅購入時のホームインスペクションの説明義務化

- 第22回 リフォーム済み中古物件に注意

- 第21回 中古住宅購入後の引渡し時の流れと注意点

- 第20回 中古住宅の内見時の注意点

- 第19回 中古住宅を購入する流れ

- 第18回 建売住宅の引渡しで失敗しないための予備知識

- 第17回 建売住宅購入時のホームインスペクション(住宅診断)の基礎知識

- 第16回 建売住宅の購入時に必要な諸費用

- 第15回 建売住宅の売買契約に関する注意点と主なチェックポイント

- 第14回 建売住宅の契約時に支払う手付金の基礎知識と注意点

- 第13回 建売住宅の購入申込と申込時の注意点

- 第12回 建売住宅の見学時における基礎的なチェックポイント

- 第11回 建売住宅を購入する流れ

- 第10回 新築住宅で利用されている住宅検査の基礎知識

- 第9回 引渡し時の注意点

- 第8回 完成時の施主検査におけるチェックポイント

- 第7回 工事着工から完成までの注意点

- 第6回 建築工事請負契約締結時の注意点

- 第5回 土地探しの基礎知識

- 第4回 工事見積もりの取り方

- 第3回 建築会社の選び方(2)建築会社選びでチェックすべきポイント

- 第2回 建築会社の選び方(1)タイプ別に見る家を建てる会社

- 第1回 注文建築で家を建てる流れ




















