第6回 建物の建築が制限されるケース
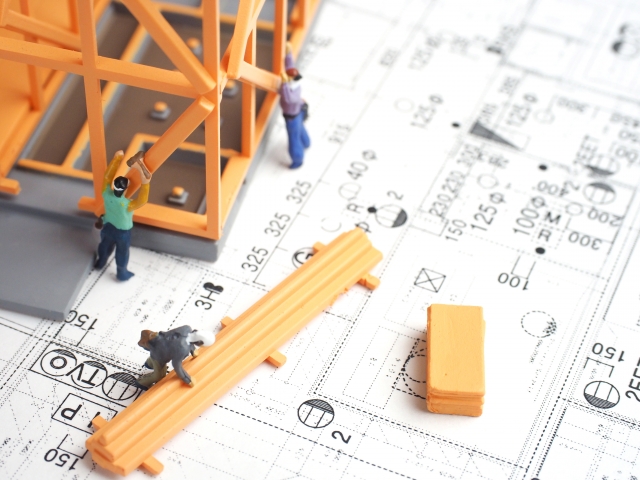
今回のテーマは、建物の建築に関する制限です。敷地部分の土地を自分が所有するなどして土地についての権原がある場合でも、自由に建物を建築できるわけではありません。今回は、建物建築が制限されるケースの代表例を見ていきます。
1接道義務
建築基準法では、都市計画区域内または準都市計画区域内においては、道路に2メートル以上接している土地でなければ建物を建てることができないとされており、「接道義務」と言われています。
この場合の「道路」とは、建築基準法42条で定義されている条件に合致する必要があり、原則として幅が4m以上あることが求められます。外形的に道の形状があれば良いわけではない点に注意が必要です。。
新しい分譲地では、既存の道路への接道が確保できないことが多く、特定行政庁から位置の指定を受けた道路(「位置指定道路」と呼ばれます。)に対して接道を確保するケースが多くみられます。ただし、位置指定道路については、幅が4m以上あっても、特定行政庁の指定を受けていなければ法律上の「道路」とは認められず、接道義務を満たすことになりませんので、土地を取得する際には、接道義務が満たされているかどうかをきちんと確認することが重要です。
また、土地が接している道路が、幅が4m未満であっても特別に道路として認められている道路(建築基準法42条2項で規定されていることから、「2項道路」と呼ばれます。)である場合、建物の建築を行う際に、道路の中心線から2m後退した線から出ないように建築することが求められ、これを「セットバック」と言います。この場合、土地の一部が道路として使用されることになりますので、土地全体に建物を建てることを想定して土地を取得すると見込み違いとなってしまうため、注意が必要です。
また、一筆の土地を複数に分ける(「分筆」と言います。)場合、分筆後のそれぞれの区画が接道義務を満たしていないと、建物が建てられない土地が生じてしまうこととなり、資産価値が極めて小さくなってしまうことが想定されますので、分筆を行う際にも接道義務への注意が必要です。
2建ぺい率・容積率

建ぺい率とは、敷地の面積に対する、建物が建っている部分の面積(建物のうち、最も床面積の大きい階の面積を基準に算定します。)の割合のことを言います。例えば、100㎡の土地のうち60㎡の部分に建物が建っていれば、建ぺい率は60%ということになります。
容積率とは、敷地の面積に対する、建物の床面積の合計の割合のことを言います。例えば、100㎡の土地に、1階の床面積が60㎡、2階の床面積が40㎡の建物が建っている場合、容積率は100%となります。
建ぺい率・容積率には、土地の用途地域に応じて上限が定められています。例えば、住居専用地域の場合、建ぺい率の上限は30%、40%、50%、60%の中から都市計画で定められます。商業地域の場合、上限は80%となります。建ぺい率・容積率ともに、住宅地においては制限が厳しく、商業地域では制限は比較的緩やかになっています。
建物の建築を予定する場合、敷地の建ぺい率・容積率の制限を満たす必要がありますので、土地を取得する段階で、予定する建物が建てられるかを事前に確認しておく必要があります。
3建物の高さの制限
建ぺい率・容積率を満たす場合であっても自由に建物が建てられるわけではなく、日照権の確保等の観点から建物の高さについても以下のような制限がありますので留意する必要があります。
(1)低層住居専用地域
低層住居専用地域では、建物の高さの上限が10mまたは12mに制限されます。したがって、この地域では通常は3階建てまでしか建てられないことになります。
(2)斜線による制限
道路の上空や隣地との開放感を保つため、敷地の境界線から一定の条件で引いた斜線内に建物を建てなくてはならないという制限です。少しイメージがしにくいかもしれませんが、この制限にかかると、敷地のぎりぎりには高い建物が建てられないということになります。
(3)日照保護のための制限
用途地域等に応じ、一定時間以上の日陰を生じさせてはならないという制限です。
4市街化調整区域
都市計画法において、市街化を抑制すべきとされる地域を市街化調整区域といいます。この市街化調整区域において住宅を建築しようとする場合、原則として都市計画法に基づく許可が必要となり、許可が得られなければ、住宅の建築はできないことになります。
したがって、住宅建築を目的として市街化調整区域を取得することには大きなリスクがありますので、土地を取得する際、市街化調整区域に該当しないことを確認しておくことが重要です。市街化調整区域に該当するかは、自治体に問い合わせれば確認することがきます。
都市計画区域内または準都市計画区域内においては、道路に2メートル以上接している土地でなければ建物を建てることができない。
用途地域により、建ぺい率・容積率の上限が異なるので、建築予定の建物が条件を満たすか事前に確認しておく必要がある。
建物の高さについても、建築基準法等による制限がある。
市街化調整区域では、原則として住宅の建築はできない。
次回のテーマは、建物建築に関する契約についての留意点です。
 このコラムの執筆者
このコラムの執筆者原田真(ハラダマコト)
一橋大学経済学部卒。株式会社村田製作所企画部等で実務経験を積み、一橋大学法科大学院、東京丸の内法律事務所を経て、2015年にアクセス総合法律事務所を開所。
第二東京弁護士会所属。東京三弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会副委員長、同高齢者・障害者の権利に関する委員会副委員長ほか
コラムバックナンバー
- 第46回 住宅(不動産)にかかわる民法改正の概要(1)

- 第45回 プライバシー侵害の救済方法(7)

- 第44回 プライバシー侵害の救済方法(6)

- 第43回 プライバシー侵害の救済方法(5)

- 第42回 プライバシー侵害の救済方法(4)

- 第41回 プライバシー侵害の救済方法(3)

- 第40回 プライバシー侵害の救済方法(2)

- 第39回 プライバシー侵害の救済方法(1)

- 第38回 プライバシー侵害の成立要件(5)

- 第37回 プライバシー侵害の成立要件(4)

- 第36回 プライバシー侵害の成立要件(3)

- 第35回 プライバシー侵害の成立要件(2)

- 第34回 プライバシー侵害の成立要件(1)

- 第33回 名誉毀損の救済方法(12)

- 第32回 名誉毀損の救済方法(11)

- 第31回 名誉毀損の救済方法(10)

- 第30 名誉毀損の救済方法(9)

- 第29回 名誉毀損の救済方法(8)

- 第28回 名誉毀損の救済方法(7)

- 第27回 名誉毀損の救済方法(6)

- 第26回 名誉毀損の救済方法(5)

- 第25回 名誉毀損の救済方法(4)

- 第24回 名誉毀損の救済方法(3)

- 第23回 名誉毀損の救済方法(2)

- 第22回 名誉毀損の救済方法(1)

- 第21回 名誉毀損の成立阻却事由(6)

- 第20回 名誉毀損の成立阻却事由(5)

- 第19回 名誉毀損の成立阻却事由(4)

- 第18回 名誉毀損の成立阻却事由(3)

- 第17回 名誉毀損の成立阻却事由(2)

- 第16回 名誉毀損の成立阻却事由(1)

- 第15回 名誉毀損の成立要件(4)

- 第14回 名誉毀損の成立要件(3)

- 第13回 名誉毀損の成立要件(2)

- 第12回 名誉毀損の成立要件(1)

- 第11回 近隣紛争(2)

- 第10回 近隣紛争

- 第9回 住宅の相続に関する問題

- 第8回 土地の境界に関する問題

- 第7回 建物建築工事契約の留意点

- 第6回 建物の建築が制限されるケース

- 第5回 不動産登記の基礎の基礎

- 第4回 法的観点からみる住宅ローン

- 第3回 売買契約締結後のトラブル(2)

- 第2回 売買契約締結後のトラブル(1)

- 第1回 住宅、土地の購入と契約の解消



















