第23回 中古住宅購入時のホームインスペクションの説明義務化
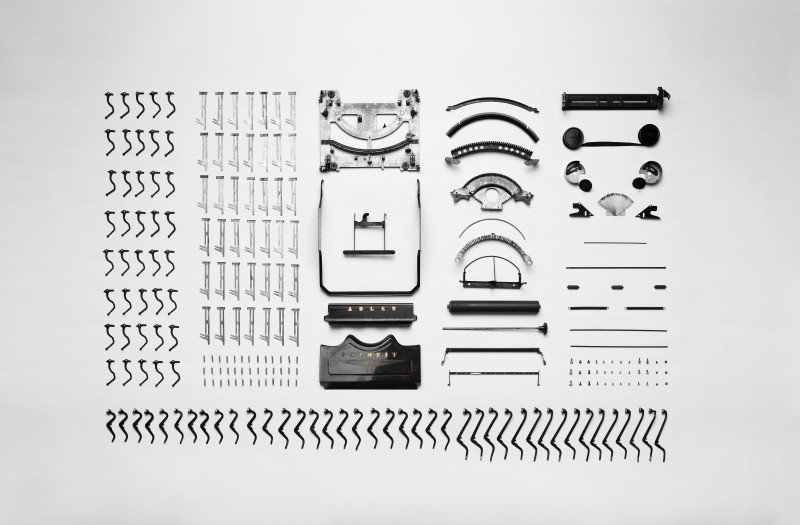
中古住宅を売買するとき、買主や売主がホームインスペクション(住宅診断)を利用する人が非常に増えました。このホームインスペクションの義務化というニュースを目にした人からの問合せも増えています。今回は、このホームインスペクションの義務化について解説します。
1中古住宅を売買するときのホームインスペクションが義務化?
2018年4月に改正宅建業法が施行されましたが、その内容の1つにホームインスペクションの説明等の義務化があります。ただ、誤解している人も少なくないので、ここで正確に理解しておきましょう。
1-1.義務化したのはホームインスペクションの説明
この法改正によって、ホームインスペクションの実施を義務化したというわけではありません。不動産会社が、売買に際して売主や買主にホームインスペクションというものがあることを説明し、利用するかどうか意思確認しなければならなくなったのです。
そして、利用したいという人には、ホームインスペクション業者を紹介できるかどうかを説明するというものです。紹介や斡旋が義務化されたというわけでもありません。
1-2.不動産業者が売主にも買主にも説明する
大事なポイントの1つは、ホームインスペクションのことを説明する対象は売主と買主の双方だということです。売主が自宅を売却しようとして不動産会社と媒介契約を締結するときには、この説明を受けられるはずです。買主は物件を見学したときや売買契約を締結する前に説明を受けられるはずです。
売主には、ホームインスペクションをしておくことによって、買主が安心して買ってくれるという期待ができます。物件のPR情報とするわけです。また、売却した後に瑕疵担保責任に基づく補修等の請求リスクを減らす効果も期待できます(インスペクションで前もって瑕疵を把握できることがあるため)。
買主には、建物の状況をよく理解した上で購入判断することができるメリットがあります。
つまり、売主にも買主にもメリットがある話だということですから、利用が広がると予想されているのです。
1-3.説明対象は簡易的な住宅診断
宅建業法の改正で説明しているホームインスペクションは、正しくは建物状況調査というもので、国交省の告示である既存住宅状況調査方法基準に基づく調査を指します。この基準の調査内容は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の調査、耐震性に関する書類の確認に限られています。
いずれも大事な点の調査ではありますが、これに該当しない劣化や建物の不具合は対象範囲に入らないため、買主にとっては本当の安心材料だと言えるか疑問が残るものです。売主は、こういったことまで知らない買主に対して安心材料をアピールできる効果が期待できるかもしれません。
買主にとっては、本来はもう少し踏み込んだホームインスペクション(住宅診断)をした方がよいとの考えもあります。つまり、説明義務の対象となっているものは、簡易的なホームインスペクション(住宅診断)だと考えておいた方が無難でしょう。

2ホームインスペクションを依頼するときの注意点
次に、売主や買主がホームインスペクション(住宅診断)を依頼するうえで注意しておくべき点を紹介します。
2-1.既存住宅売買瑕疵保険の加入も検討する
中古住宅の売買に際して加入できる保険があるのを知っていますか?既存住宅売買瑕疵保険というものですが、これに加入している物件ならば、購入後に発見された雨漏りや構造耐力上主要な部分の事故について補修費用等が保険金で賄われるというものです。
特に雨漏り事故は日本全国で非常に多く起こっていることから、助けになることも少なくありません。
ホームインスペクションを依頼するならば、既存住宅売買瑕疵保険に加入できるかどうか、ホームインスペクション業者に相談するとよいでしょう。
但し、既存住宅売買瑕疵保険の基準は少々厳しく、不適合となるケースは多いです。実績あるホームインスペクション業者に相談しながら進めるとよいでしょう。
2-2.買主なら売主側のホームインスペクションでよいか検討する
ホームインスペクションを依頼するのは、売主でも買主でもありうることです。買主がホームインスペクションを希望している旨を不動産会社へ申しでたところで、売主が実施しているから大丈夫だと説得されることも増えました。
そのホームインスペクションが、信頼できるものであり、且つ十分な内容のものならばよいのですが、前述のとおり「構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分」に限定したものであることがほとんどです。それも、詳細まで確認していないことが多く、買主にとって本当に欲しい情報が網羅されていないため、買主は自らホームインスペクション業者を探して依頼することを考えた方が無難です。
売主が不動産会社経由で依頼しているホームインスペクションは、簡易的な住宅診断であり、報告内容もシンプルで詳細不明ということが一般化している現状があるのです。
また、筆者の会社(アネストブレーントラスト)にも不動産会社から問合せが入ることがありますが、営業マンから「多少のことは目をつぶってほしい。仕事はいくらでも紹介できるから」などと言われたことが何度かあります。驚くべきことですが、物件が売れないと売上も歩合給も入らない立場の人だけに、そういう人がいるのもこの業界の残念な事実です。
当然、アネストではそういう話はすぐに断るわけですが、仕事ほしさに受ける業者もありますから、できればホームインスペクション業者探しを不動産会社任せにせず、自分で探した方が無難です。
2-3.買主ならスピードが大事
買主がホームインスペクションを依頼するときは、多くの場合において売買契約の直前です。購入する物件を決めてから契約するまでの間に利用するわけですが、早く依頼して診断してもらわないと、他の人が先に購入することもあるため、スピード感が大事です。早めに依頼することを心がけましょう。
2-4.売主なら報告書の質・量を比べてインスペクション業者を選ぶ
売主がホームインスペクションを利用する場合、前述したとおり不動産会社経由で簡易な住宅診断をしていることが非常に多いですが(全てではありません)、報告書も非常にシンプルなものであるため、買主への説得材料として弱い部分もあります。
売主も自分自身でホームインスペクション業者を探して、各社の報告書の質・量・内容を比較検討して利用した方がよいでしょう。同じ利用するならば、より意義の高い方法を選んでみることです。
2-5.床下や小屋裏まで調査してもらう
売主にも買主にも言えることですが、一戸建て住宅のホームインスペクションを行うならば、ぜひ床下や小屋裏内部まで調査してもらう方がよいです。
普段は見ることのないスペースですが、土台・柱・梁などの大事な構造部分を目視調査できる箇所であり、雨漏りやシロアリ被害が確認されることもあるところでもあります。また、室内の快適性やエネルギー効率(エアコンの効率など)に影響ある断熱材の状態まで確認できるのもメリットです(但し、簡易な住宅診断では断熱材まで確認しない)。
床下や小屋裏の内部にホームインスペクターが進入できるだけのスペースがあるならば、別途料金を支払ってでも潜って調査してもらった方がよいです。
売主でも買主でも、中古住宅の売買に際して利用するホームインスペクションの検討に役立ててください。
 このコラムの執筆者
このコラムの執筆者荒井 康矩(アライ ヤスノリ)
2003年より住宅検査・診断(ホームインスペクション)、内覧会同行、住宅購入相談サービスを大阪で開始し、その後に全国展開。(株)アネストブレーントラストの代表者。
コラムバックナンバー
- 第25回 耐震性を考えるなら新耐震基準の中古住宅購入(最終回)

- 第24回 中古住宅を買うなら住宅ローン控除の手続きを忘れないように

- 第23回 中古住宅購入時のホームインスペクションの説明義務化

- 第22回 リフォーム済み中古物件に注意

- 第21回 中古住宅購入後の引渡し時の流れと注意点

- 第20回 中古住宅の内見時の注意点

- 第19回 中古住宅を購入する流れ

- 第18回 建売住宅の引渡しで失敗しないための予備知識

- 第17回 建売住宅購入時のホームインスペクション(住宅診断)の基礎知識

- 第16回 建売住宅の購入時に必要な諸費用

- 第15回 建売住宅の売買契約に関する注意点と主なチェックポイント

- 第14回 建売住宅の契約時に支払う手付金の基礎知識と注意点

- 第13回 建売住宅の購入申込と申込時の注意点

- 第12回 建売住宅の見学時における基礎的なチェックポイント

- 第11回 建売住宅を購入する流れ

- 第10回 新築住宅で利用されている住宅検査の基礎知識

- 第9回 引渡し時の注意点

- 第8回 完成時の施主検査におけるチェックポイント

- 第7回 工事着工から完成までの注意点

- 第6回 建築工事請負契約締結時の注意点

- 第5回 土地探しの基礎知識

- 第4回 工事見積もりの取り方

- 第3回 建築会社の選び方(2)建築会社選びでチェックすべきポイント

- 第2回 建築会社の選び方(1)タイプ別に見る家を建てる会社

- 第1回 注文建築で家を建てる流れ





















